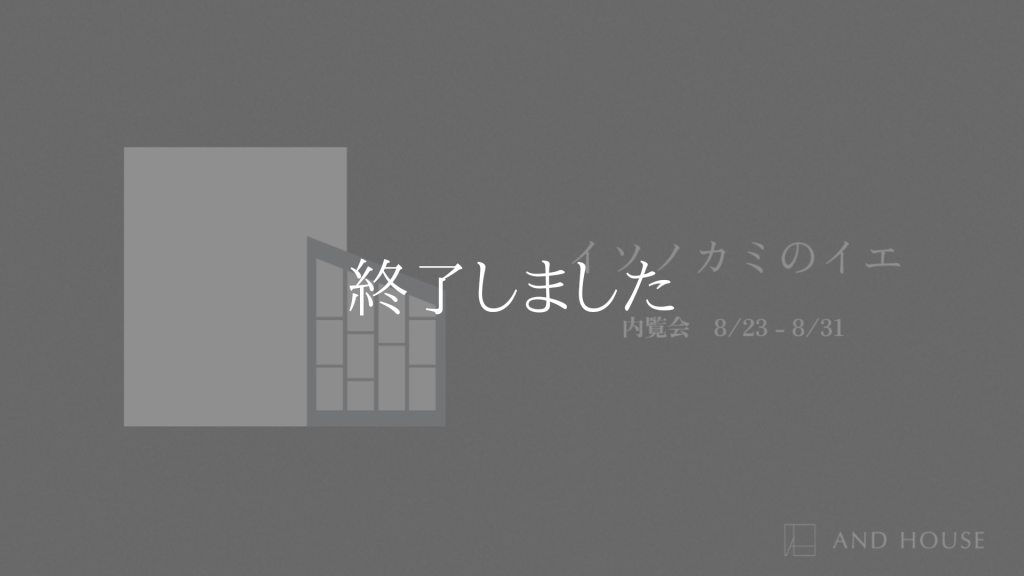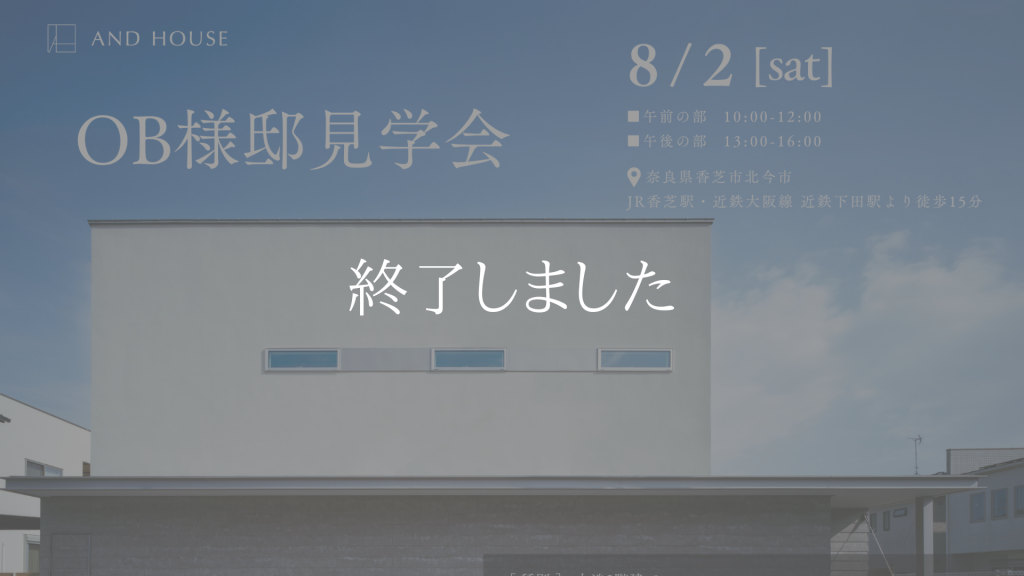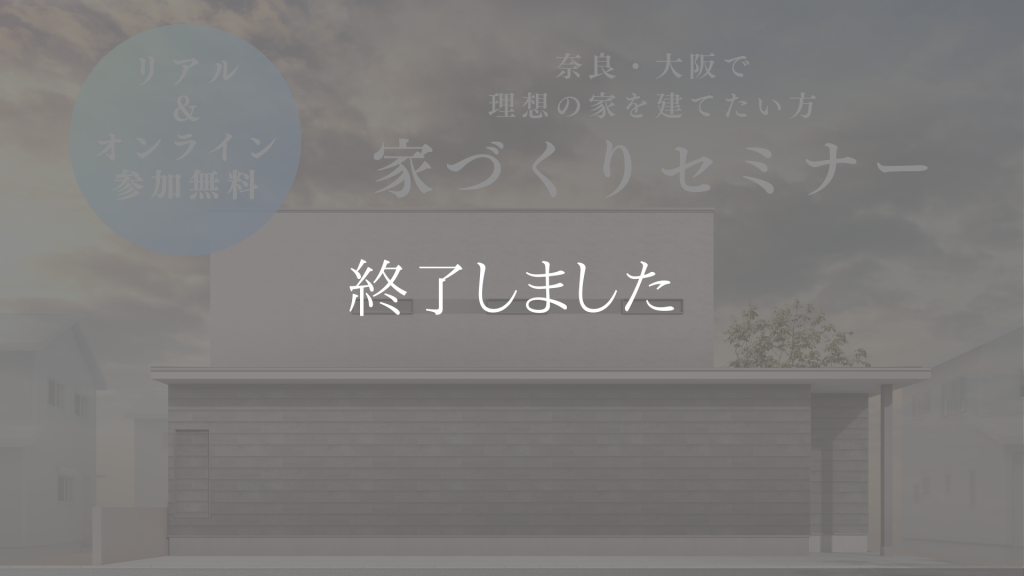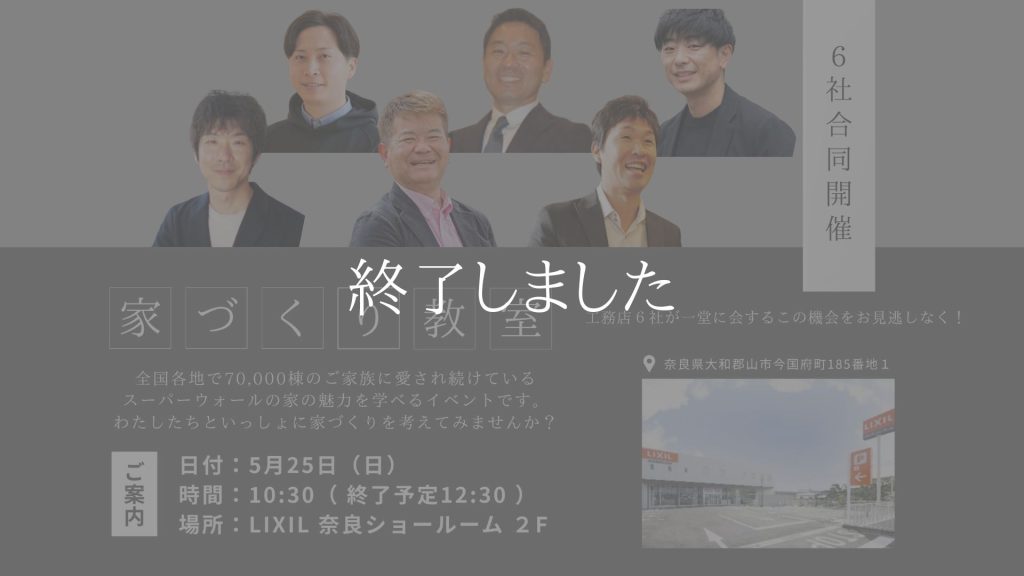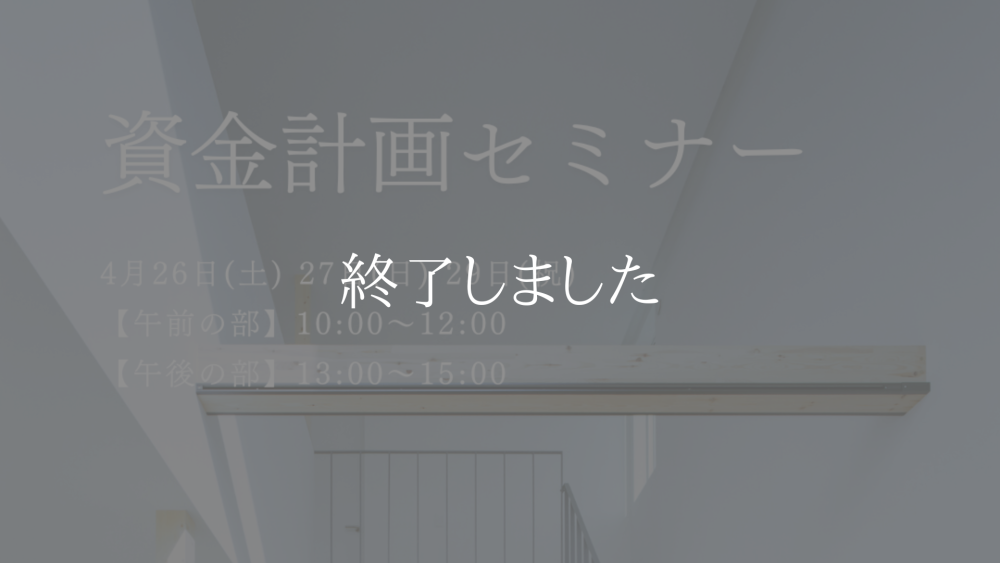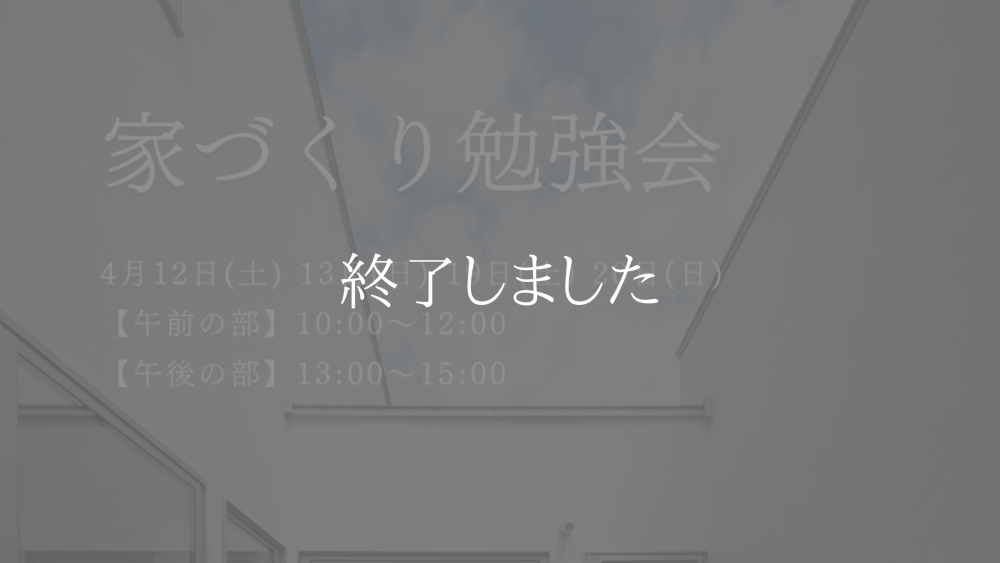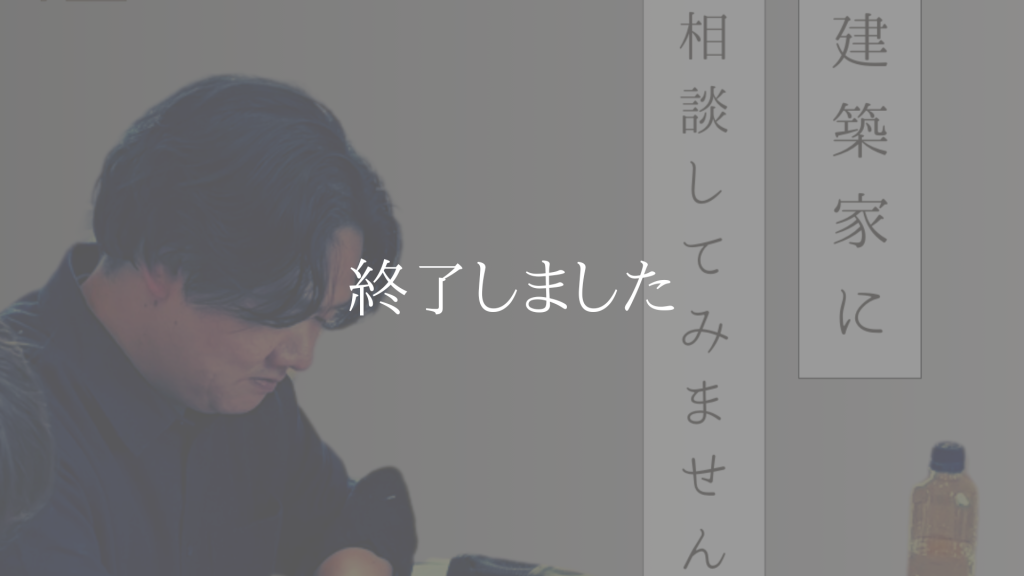WORKS
マイホーム計画をはじめるとき、何から考えるでしょうか?
お金、土地、間取り・・・たくさんありますが、まずは「どんなふうに暮らしたい?」から考えてみてはいかがでしょうか。
あなたの理想の暮らしをイメージすれば、求める家の形がはっきりしてくるはずです。
家族でゆったりスローライフ

休日は日向ぼっこをしながらごろごろ。リビングは寝転がっても気持ちがいい無垢の床材と、たっぷりと光が入ってくる大きな窓。
起きたら家族みんなで、家庭菜園のお世話。庭に小さな畑があれば、とれたての野菜を食卓に並べることができます。
体を動かしたら、大人はまたのんびりと休憩。まだまだ元気な子どもたちが庭で遊ぶようすを、リビングでゆったりと見守れるといいですね。
家族や仲間とわいわい楽しくにぎやかに

休日には友人を家に呼んで、バーベキューやホームパーティー。みんなが集まるリビングは、吹き抜けと大きな窓で開放的な空間に。広々としたキッチンなら、みんなでわいわい料理を楽しめるでしょう。普段の料理ももっと楽しくなります。
ウッドデッキや中庭とリビングをつなげるのもおすすめ。家と外を気軽に行き来しながら、アクティブに過ごせるおうちになります。
アウトドアグッズをたくさんそろえるなら、収納もたっぷりとほしいですね。
趣味に没頭する一人の時間も大切に

家族の時間も大切だけれど、自分ひとりで趣味や仕事に熱中する時間も大切にしたい。そんんな理想があれば、ひとりでこもれる秘密基地のような書斎を。
本好きの家族なら、壁一面に本棚をつくって、おうち図書館に。大好きな本をいつでも手にとり、お気に入りのチェアに腰掛けて、ゆっくり本の世界を楽しめます。
子どもの学習スペースをリビングにつくれば、家族のそばで安心して勉強に集中。持ち帰りの仕事や、パソコン作業のスペースとしても使えます。
まとめ
あなたや家族が理想とするのはどんな暮らし、どんな時間の使い方でしょうか?
住宅展示場で見たおうちがどれだけ素敵でも、あなたの家族の理想とする生活が叶うとは限りません。新しくつくった家でどんな暮らしをしたいのか、考えるところからはじめてみてくださいね。
私たちはご家族と同じ目線に立って、「どんな暮らしがしたいのか?」「そのためにはどんな家づくりをするべきか?」本質から一緒に考えさせていただきます。単なる図面をつくるのではなく、ご家族の夢や希望を話してみてくださいね。
リラックス効果があり、私たちのストレスを和らげてくれる植物たち。「kokage Salon」では、暮らしをおしゃれに彩り、心身の健康を助けてくれる、自然を取り入れた家づくりを推奨しています。今回は、緑のある暮らしを実現する、住まいのアイディアをご紹介します!
リビングと庭をつなげる

リビングと庭を大きな窓でつなげると、緑豊かな庭をぞんぶんに楽しめる住まいに。リビングにいながら外の景色を楽しむことができ、庭で子どもたちが遊ぶようすも目に入ります。
せっかく庭をつくるなら、たまに使う場所ではなく、日常的にフル活用できる場所にしたいもの。リビングの床と段差をつけず、ウッドデッキやテラスを設けると、気軽に庭に出ることができますよ。
デッキ近くには、シンボルツリーを植えて。美しい緑を目で見て楽しめるだけでなく、暑い日の日除けや、外からの目隠しにもなります。
ガーデニングを楽しむ

最近は、お庭で花を育てたり、家庭菜園を楽しんだりする人も多いですよね。
天気の良い週末には、家族で庭いじりを楽しんでみてはいかがでしょうか。自然に触れられるだけでなく、お子さんの食育にもなりますよ。
家庭菜園って、大きな畑が必要なのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、ご安心を。1~2坪の小さなスペースからでも、ガーデニングははじめられますよ。慣れてきたら、どんどん畑を広げていくのも良いですね。
インテリアグリーンを取り入れる

庭だけでなく、家のなかにも緑のある暮らしを。グリーンをうまく取り入れれば、インテリアがぐっと格上げされます。
観葉植物を選ぶコツは、お部屋のインテリアに合わせて、背の高さ、葉の形やボリューム、デザインを選ぶこと。大きな鉢植えを置く場所がなければ、「ハンギングバスケット」で窓際や壁に吊るすのもおすすめです。
まとめ

緑を見ながらゆったりとコーヒーを淹れる、子どもといっしょに畑づくりをしていい汗をかく、グリーンのある素敵なインテリアのお部屋で友人たちと楽しく過ごす・・・。
みなさんは、どのように緑のある暮らしを楽しみたいでしょうか?
私たちは、地域にも暮らしにも優しい、自然に溶け込むような木の家をつくっています。人や暮らしを豊かにする家づくりで、あわただしい日常を、快適でゆとりある生活に変えてみませんか☆
住宅の構造には、木造意外にも鉄骨造(S造)・鉄筋コンクリート造(RC造)などさまざまあります。私たちが提供しているのは、ぬくもりのある木の家。構造だけでなく、床などの内装にもふんだんに木を取り入れています。
『木の家』のメリット
心地よい温もり・肌触り・香り

なんといっても、裸足で歩いたときの温かみや柔らかさ、リラックス効果のある香りが魅力!それに加え木材は『調湿作用』をもち、お部屋の湿度をいつも快適に保ってくれます。ジメジメと湿気の多い日には余計な水分を吸い、乾燥した日には水分を放出。高温多湿の日本にぴったりな素材です。
将来的にリフォームしやすい

木造住宅は主に「在来工法(柱や梁で支える)」「2×4工法(壁で支える)」の2種類に分けられます。大手ハウスメーカーでは2×4工法のこともありますが、ほとんどの工務店では在来工法が採用されています。
在来工法は柱・梁などの『線』で支えるので、壁を動かしたり撤去したりしやすいのが特徴。間取りの自由度が高く、将来的なリフォームもしやすいんですよ。
何十年と長く住める

日本には、1000年以上も前に建てられた木造建築物がいくつも残っています。きちんと建てて、きちんとお手入れをすれば、何世代にもわたって住むことができるのです。
床などに使われる無垢材は、年月とともに色が濃く、深みを増していきます。傷もつきますが、それも良い味わいに。使えば使うほど、魅力的になっていくのも、木の家のメリットです。
『木の家』の疑問&デメリット
火事で燃えやすいのでは?

木材は可燃性の素材。鉄やコンクリートに比べると燃えやすいのは事実です。しかし意外なことに、木の家は、鉄より火災に強いともいわれています。
鉄は火災で高熱にさらされると、一気に強度を失ってグニャリと曲がってしまいます。
一方、柱や梁のように太い木材は、表面が焦げるのみ。『炭化層』ができて芯まではなかなか燃えないので、十分な避難時間が確保できるというわけです。
耐久性は大丈夫?

木造住宅で気をつけたいのが、シロアリ被害・湿気・雨漏りによる腐食です。
①シロアリの被害に合いにくい樹種を選ぶ、②適切な防蟻処理をおこなう、③結露・雨漏りしないよう施工することで、長く快適に住むことができます。
まとめ
木材は一つひとつ個性を持っており、湿気の含み方による伸縮もある素材。長く住める木の家を建てるには、木の性質に合わせてきちんと施工することがとても大切です。
これから住宅会社を検討される方は、その会社がどんな木材を使われているのか、こだわりをもって建てているのか、しっかりと確認されてくださいね。
今、子どもたちを悩ませる病気で、最も多く聞くのがアレルギー疾患。アトピー性皮膚炎や喘息、鼻炎など、実に2人に1人が何らのアレルギーを持つと言われています。
また建材に含まれる化学物質を原因とした「シックハウス症候群」が話題になったことからも、自然素材を使った人にも環境にも優しい住宅が注目されています。
私たちの家づくりでは、床や壁などの肌に触れる部分には、なるべく無垢材や漆喰、紙クロスなどの自然素材を使用しています。
子どもも大人も健康的に暮らせる

シックハウス症候群を引き起こすのは、住宅に使われる建材から発生する化学物質。例えばビニールクロスや合板を貼り付ける接着剤に含まれるホルムアルデヒドなどが人体に影響をおよぼすと言われています。
自然素材の家では、そもそもそういった化学物質を含まない素材や、化学物質を吸収・分解する漆喰などの素材を使うことで、体への害をなるべく少なくしています。
心地よい香りや肌触りが楽しめる

無垢フローリングを裸足であるくと、ほどよいぬくもり感とやわらかさ。冬場も冷たくならず、気持ちの良い肌触りを楽しめます。また自然木の良い香りもするので、心もリラックスできますよ。ぜひ実際に触れて、気持ちよさの違いを感じてみてください。
調湿作用で自然と快適な空気に

無垢材も漆喰も「調湿作用」を持っています。つまり呼吸をするように、ジメジメしたときには湿気を吸って、乾燥しているときに放出してくれるのです。
梅雨や夏の蒸し暑い時期には室内をサラッとさせ、冬の乾燥しすぎは防いでくれます。カビやダニ、結露の対策にもなりますよ。
住めば住むほど愛着のわく家に

合板のフローリングというのは、年とともに劣化していくもの。それに対して無垢材を使うと、年を重ねれば重ねるごとに、味のある風合いに変化していきます。色は徐々に深い飴色に、艶は増してますます美しく。住むほどに愛着がわく、そんな理想の家になることでしょう。
まとめ
体への優しさだけでなく、見た目にも美しい自然素材。しかし人間一人ひとり顔や性格が違うように、自然素材は一つひとつの材料に個性があります。環境によって曲がりやねじれもでてくるので、失敗しないためには、自然素材の特徴と扱い方を知り尽くした工務店や職人さんに依頼することが大切です。

私たちは、赤ちゃんからお年寄りまで安心安全に住める家をご提案させていただきます。自然素材の家に興味がある方、人と暮らしに寄り添う家づくりがしたい方は、ぜひご相談ください。
トップライト(天窓)とは、屋根や天井に設置された窓のこと。吹き抜けにつくると、光がふんだんに入ってきて、すごくおしゃれな空間になります。
今回は、トップライトの魅力をご紹介。「雨漏りしない?」「メンテナンスは?」などの疑問にもお答えしたいと思います。
吹き抜けにトップライトをつくるメリット

メリット1|採光
一般的な壁面の窓に比べて、トップライトは3倍の採光効果があるとされています。壁面窓なら限られた時間しか光が入りませんが、トップライトなら昼間のほとんどの時間、一定の光量が得られます。朝からたっぷりと光を浴びることで、体内時計も整い、心や体に良い影響を与えるでしょう。
メリット2|開放感
トップライトを通して、上方へと視界が抜けるため、リビングに広がりを感じられます。青空や星空を見上げることもできるので、お子さんの健康な心身を育みたい、自然とふれあいながら育ってほしいという方にもおすすめです。
メリット3|プライバシー性
大きな窓をとりたくても、隣家や周辺道路の位置によっては、視線が気になることもあるでしょう。トップライトなら、プライバシーや防犯面をクリアしつつ採光がとれます。
吹き抜けのトップライトで気になる疑問&デメリット

雨漏りはしないの?
トップライトは屋根に穴を開けてはめ込むので、雨漏りリスク回避のため、製品ごとに屋根の勾配が決められています。また各メーカーで「水密性・気密性・台風暑性」の3つのテストを受けており、強い圧をかけても水が入らないと確認されているので安心です。窓自体の防水性能は高いので、あとは信頼できる業者に正しく施工してもらいましょう。
夏場の暑さやまぶしさは?
室内が明るくなるということは、それだけ夏の日差しをダイレクトに受けるということ。しかし遮熱性の高いガラスを選べば、熱が入りすぎることはありません。また、遮光カーテンやブラインドを取り付けて、入ってくる光を調整することもできます。
どうやって掃除するの?
トップライトはなかなかご自身で掃除されるのは難しいです。室内からは、柄の長いモップが売られているので、そちらで拭き掃除をされてください。外側は業者に頼むのが無難。メーカーによっては、アフターメンテナンスが受けられることもあります。汚れがつきにくいガラスや、回転して外側掃除できる商品を採用されるのも良いでしょう。
まとめ
吹き抜け×トップライトは採光性やプライバシー性などの魅力がありますが、暑さや雨漏りなどの不安も。ぜひ吹き抜けの得意な工務店に相談して、アドバイスをもらってくださいね。
これまで『庭・畑づくり』シリーズのコラムで6回にわたって、たくさんのことを紹介させていただきました!
いかがだったでしょうか?参考にしていただければと思います☆
そこで、今回は『庭・畑づくり』のまとめで振り返っていきましょう!
庭・畑が与える効果

『庭・畑のある暮らし』では、自然を身近に感じ、触れる機会を作ることができ、緑に癒され、樹木や草花から四季を感じることもできます。感受性が豊かになったり、庭のお手入れをすることで運動不足の解消。庭の草木がマイナスイオンを与えてくれる。心理的にも身体的にも環境的にも効果を与えます。
子どもと楽しむ食育・土育

『食育・土育』のコラムでは畑で収穫した野菜を使って、子どもと食べることを楽しみ、畑の土を触ることで様々な感性が刺激されるので感受性が育まれると言われています。『食育・土育』と言うと難しそうなイメージかと思いますが、庭・畑があると気軽にできることだと思います☆
育てやすい木・野菜

『育てやすい木』ではアオダモ、カツラ、ジューンベリー、レモン、オリーブを紹介しました。モデルハウス「kokage Salon」にもアオダモ、カツラ、ジューンベリーを庭に植えています!また『育てやすい野菜』で紹介していなかった野菜もたくさん植えているので、モデルハウス「kokage Salon」にぜひ見に来てくださいね!
今オススメの樹木・野菜
 『今オススメの樹木・野菜』で紹介した、イロハモミジやキンモクセイ。モミジは秋の季節に色づいて、緑色だった葉が黄色、赤色に変化していく様子は眺めていると自然を身近に感じることができます。モデルハウス「kokage Salon」にあるモミジも赤色に変化して毎日の癒しになっています♪
『今オススメの樹木・野菜』で紹介した、イロハモミジやキンモクセイ。モミジは秋の季節に色づいて、緑色だった葉が黄色、赤色に変化していく様子は眺めていると自然を身近に感じることができます。モデルハウス「kokage Salon」にあるモミジも赤色に変化して毎日の癒しになっています♪
お手入れ方法

『お手入れ』で紹介した方法は初心者の方にも簡単にできる方法です☆はじめは難しいと思うかもしれませんが、慣れてくると簡単にできるので試してくださいね!
まとめ
みなさん気になるコラムはありましたか?
家を建てるときは植物を植えて、心も身体も健康におうちで過ごしていただきたいと思います。また、育てた野菜を収穫したり、今オススメの樹木・野菜編でご紹介した『イロハモミジ』の紅葉を鑑賞して楽しむのもいいですね!紹介したお手入れ方法で植物を大切にしながら、『庭・畑のある暮らし』を楽しんでいただけたらなと思っています。
おうちに『庭・畑』があると楽しみ方はたくさんです☆みなさんも『庭・畑のある暮らし』を体験していただきたいと思います。
注文住宅を建てるなら、土地が必要。お子さんがいるご家庭の場合、エリアや広さはもちろん「子育てしやすい土地に住みたいなぁ」という思いを持たれる方も多いのでは?
今回は、子育てファミリーがどのようなことに気をつけて土地を探せば良いのかについて考えてみたいと思います。
希望するエリアや条件を洗い出す

まずは、どんな土地に住みたいか、希望される条件をたくさん書き出してみましょう。夫婦2人のときには気にならなかったポイントも、子育て中は優先順位が少し変わってくるはず。
学校・会社
「◯◯小学校の学区内がいい」といった条件や、通学路の安全性などを気にされる方は多いのでは?あわせて大人の通勤についても考えたいですよね。
自治体
子育て支援の内容は、自治体によって異なります。共働きなら、保育園の空き状況や学童への入りやすさも重要なポイントに。
周辺環境
小さなお子さんを連れてスーパーや駅まで移動するのは一苦労。車を使うのか、バスや電車を使うのかによっても、求める条件は変わってくるでしょう。
その他
実家から近いエリアで土地を探される方も多いです。また独身時代は昼間家にないことも多いですが、子供がいると日当たりなども気になってきますよね。周辺にファミリーが多い地域なのか、単身者が多い地域なのかというのもポイントです。
その土地に何年住むか考えてみる

例えば35歳で家を買って、90歳まで住むとすると、55年はその土地で暮らすことになりますよね。もしかすると今は「◯◯学区がいい」という条件が大切かもしれませんが、子供が卒業して、巣立っていき、仕事を退職して・・・と長い人生を考えると、優先順位が変わってくるかもしれません。
子育て期
子供が0~18歳ごろ、子育てまっただなかの時期。何かと子供中心に生活が回って行くでしょう。子供の安全と健やかな成長、仕事や子育ての両立などを重視。
巣立ち期
子供が自立すると、夫婦2人での暮らしがやってきます。夫婦共働きなら、70歳くらいまでは仕事もあり、まだまだ忙しいかもしれません。
シニア期
70歳で定年退職を迎え、90歳まで生きるとしても、20年前後あります。車を運転しなくなって、買い物や病院への交通手段が変わる可能性も。
周辺地域を歩いてみる

だいたいのエリアや希望の土地が決まったら、現地を歩いてみることをおすすめします。学校・幼稚園・スーパー・駅までの道はどうでしょうか。「安全な歩道はあるか」「車や自転車の往来はどうか?」など子供の視点で確認してみましょう。
晴れの日だけでなく、雨の日や夕方、夜も歩いてみるといいですよ。「昼はにぎやかな公園も、夜は見通しが悪い」「大雨で地面がぬかるむから雨の日の外出がしにくそう」など新たな発見があるかもしれません。
まとめ
今回は子育て中の土地探しのポイントをお伝えしました。現在のことも考えつつ、将来のことも大切にしていきたいですよね。すべての条件がそろう土地は価格も高いもの。先々のお金のことも考えながら、納得いく住まいを作っていきましょう。
庭や畑にどのようなイメージを持っていますか?「お世話や管理が大変そうだなぁ」と感じる方が多いかと思います。
樹木のお手入れで最も大事なのは剪定なのですが、簡単にできる剪定方法があります。今回はその剪定方法のお話と、注意しておきたい病気・害虫のお話を合わせてご紹介させていただきます!
剪定の目的
1. 形を整え、生活に適した樹形を作るため(家庭の庭など、限られた場所の中で高さや広がりを制限する)
2.日当たりや風通しをよくするため
3.花つきや実つきをよくするなど、木の育成を促進したり、逆に育成を抑えるため

剪定は好きな時にできるわけではありません。基本は、毎年夏と冬の2回ですが、木の種類によって時期がさまざまです。剪定の時期を間違えてしまうと、花や実を楽しめなくなるだけでなく、切り口から樹液が流れ出して木を枯らせてしまうこともあります。
剪定したい樹木の時期をきちんと確認してから剪定してみましょう!
剪定方法が木の場所によってさまざまあるのですが、今回は中でも注意の必要な太い枝の切り方をご紹介します。
太い枝の切り方
太い枝は、上から切ると枝の重みで途中で折れてしまい、樹皮が剥がれてしまったり損傷がとても大きくなってしまいます。枝を守るため、手順を間違えないよう気を付けて切っていきましょう。
①下から1/3程度までノコギリで切り込みを入れます。
②先ほど切り込みを入れた位置から少し枝先よりに離れた位置を上から切りましょう。
③上下から切り込みを入れた枝を切り離し、最後に付け根から切りましょう。
※太い枝を切った後には、植物へのダメージを最小限に抑えるために、木の切り傷(=切り口)を保護する役割の癒合剤などを塗っておくと良いでしょう。
※付け根から切らず切り口を長く残してしまうと、見た目が悪いだけでなく、その部分が枯れてしまったり、病気の原因になったりすることがあるので注意が必要です。
自分で剪定を行う際には、山などに自然に生えている、人の手が入っていない木をお手本にして、樹形を合わせるように切っていくことをおすすめします。近くに自然に生えている木がない場合は、庭師さんなどが剪定をしたあとの木を参考にして剪定してみてくださいね◎
病気・害虫

チャドクガ
ツバキ科などの樹木に発生し、毒を持つ毛虫の中でも最も有名な虫のひとつ。茶褐色のケムシが葉を食い荒らします。
チャドクガは毛虫である幼虫時代から成虫になってもずっと毒を持ち続け、毒針毛に触れると激しいかゆみと発疹があらわれます。
毒針毛は非常に細かいので、繊維のすきまから入り込むことがあります。また、直接触れなくても木のそばを通っただけで被害にあうこともあります。針が肌にくっついたり刺さってしまうととにかく痒いです!!
対策は、冬のうちから葉裏の卵塊を探して除去し、剪定も行い、まず風通しをよくしておきましょう。
幼虫の初期の段階であれば枝や葉をビニール袋で覆し、切り取りましょう。
作業は毒針が風に乗って飛び散ってしまう可能性があるので、必ず風のないときを選び、帽子に長袖、手袋、マスク、めがね、首にタオルを巻くなどして肌を露出しないようにして、毒針毛が皮膚に触れないよう気をつけましょう!
毛虫が死んでも毒針毛はそのままなので、死骸や樹木に残っている毛にも注意が必要です。
家庭での駆除が難しいと感じたときは、専門の駆除業者へ相談、依頼することをおすすめします。
テッポウムシ(カミキリムシの幼虫)
幹に穴があいているとそれはテッポウムシかもしれません!テッポウムシはモミジなどに穴をあけて幹の内部から食べていくので、被害に気がついた時にはもうすでに木が弱っていたりする事があります。
大きな穴を見つけたら、株が弱っていないか、根本はグラグラになっていないかなどよく確かめ、穴の中に幼虫がいる恐れがあるので農薬を噴霧してから穴を塞ぐことが大切になるので、気を付けて対策してくださいね!
まとめ
お世話や管理が難しそうだなぁと感じる庭のお手入れ。
大事な庭木なので、プロの手に任せるのが一番かもしれませんが、自分の手で剪定してみるのもますます愛着が湧きそうでいいですよね!
手をかけ愛情たっぷり自分で作るお庭づくり。草取りや草刈り、枯葉の掃き掃除など重労働もありますが、その分、お家から眺めるお庭は素敵なものになるかと思います、、、☆
秋が深まるにつれて、紅葉が美しい場所にお出掛けもしたいところですが、お庭に植物があれば自宅で秋を感じることができます。
お庭を眺めながらお家でゆっくり過ごすことで、季節の移り変わりを身近に感じることができ、忙しい日常からほっと一息、心が癒されますね。
そこで今回は秋冬に葉に色を付け楽しむことができるおすすめの樹木、そして秋に種をまき、冬や春に収穫できるおすすめの野菜をご紹介します♩
イロハモミジ

落葉樹の高木で秋の紅葉を楽しむ代表的な庭木がイロハモミジです。和風に合う紅葉が美しい樹木です。
7裂している葉の裂片を「いろは…」と数えたことが名前の由来になっています。
1年を通して葉に日が当たる場所がいいと言われていますので、日陰に植えることは避けましょう。
春の新芽が開く、4~5月ごろに花が咲いた頃、花と葉を一緒に眺めるととても美しいので、ぜひ眺めてみてくださいね!
キンモクセイ

秋の訪れを知らせてくれる、キンモクセイの香り。9月ごろの開花期にオレンジの小花を枝いっぱいにつけるので、その香りとともに、遠くからでもよく目立ちます。
低温、多湿になると特に香るので、夜間は、近くになくても香りを感じられます。
秋の夜は、夏が終わり風も強くなって肌寒い。。そんな季節の変わり目を知らせてくれる香りですね!
夏の高温多湿にも耐えることができるので丈夫に育ちますが、やや寒さに弱いので、霜が降りるような場所では生育は不良となり、また大気の汚れた場所では花つきが悪くなるので、注意が必要です。
放っておくと全体に広がりすぎてしまうので、毎年剪定をしてお庭に合った大きさに仕立てます。刈り込みなどで仕立てられることも多いです◎
タマネギ

タマネギは9月~10月上旬に種まきを行いますが、種からタマネギを育てようと思うと、少し手間ひまを要してしまいますので、初めて育てる方や、畑仕事に慣れていない方には、10月~11月ごろに出回る、苗の購入をおすすめします。
タマネギ苗は、元気すぎるものを購入すると、収穫時に葉だけが立派に育ってしまい玉が大きくならないことがあるので、ほどほどに元気な細めのものを選ぶほうが良いと言われています。畑に植え付ければ元気になります!
タマネギには「早生」「中生」と種類があり、11月ごろに定植すると翌年の3月~6月ごろには収穫可能になります◎
早生品種は、収穫してすぐだと生で食べてもやわらかく、中晩生品種は長期の保存ができるので、ご希望の種類の苗を購入してくださいね!
ホウレンソウ

栄養満点なホウレンソウは初めて家庭菜園に挑戦する方でもぴったり、育てやすい野菜といわれています。
ホウレンソウは種から育てることが多く、種まき後1か月〜2ヶ月で収穫時期を迎えるので、育てがいを感じやすく、真夏をのぞいてほぼ1年中栽培することができるのも嬉しいポイントです♩
品種によって、冬でも栽培が可能な品種もあるので、収穫したい時期や栽培を始めたい時期に合わせて品種を決めるのもおすすめです◎
注意することといえば、乾燥が苦手なので、水はたっぷり(吸収が鈍る夕方までに)あげてくださいね。
キャベツ

キャベツは種まきのタイミングにより1年を通して収穫ができる野菜です。
種からまいても育てられますが、初めての方であれば、苗から育てた方が収穫まで上手く育てられます♩
キャベツは春まき、夏まき、秋まきと、まきどきが3回ありますが、比較的冷涼な気候を好む(生育適温は15~20℃)ので、夏の終わりから秋の初めのちょうど今頃の時期に苗を購入して育て始めることがおすすめです◎
キャベツは定植してから2ヶ月~3ヶ月で収穫時期を迎えます。手でギュッと押さえてみて、固く締まっていたら収穫時期です。ふわっとやわらかいようであれば、もう少し様子を見てください。球が小さくても、固く締まっている場合はそれ以上は大きくならないので収穫してしまいましょう!
収穫が遅れてしまうと割れたり、葉が固くなったりしてしまい味が落ちるので、採り遅れには注意してくださいね。
まとめ
秋の景色といえば紅葉。名所での紅葉も素敵ですが、自宅の庭で移り変わる季節を楽しめたら、それだけで生活がぐっと楽しくなりますよね。お庭に1本あるだけで、がらっと自宅のお庭の風景を変えてくれる存在になります◎
毎日変化していく葉の色を眺めながら、季節の移ろいを感じ、また紅葉の色合いや時期が毎年少し変わるので、今年の紅葉はどうかな? と日々観察していると、自然を身近に感じることができるかと思います☆
そして秋冬の家庭菜園。秋冬の野菜の栽培は、春夏の野菜の栽培よりも病害虫が少なく、初心者でも立派な野菜が収穫できるのでおすすめです◎
寒さに強いものが多いですが、あまりに温度の変化がある場合はしっかりと寒さ対策をしましょう。
葉もの野菜と根もの野菜が中心になりますが、お気に入りの野菜をたくさん育ててくださいね♩
自宅で育てた採れたての野菜をそのまま食卓で味わうことのできる家庭菜園。初心者でも上手にできる方法があります!
ほとんどの野菜は種を撒いてから意外と栽培サイクルが早いので、飽きる間もなく、また季節によって育てられる野菜が変わるので、年間を通じて楽しめるのも嬉しいポイント♩
始めてみたいけど、少し不安。簡単に始められて、失敗しづらいものから栽培したいですよね!そんな、何から栽培しようか迷っている方におすすめの野菜を紹介します。
育てやすい野菜
ミニトマト

ミニトマトは大きなトマトとは違い比較的育てやすい野菜で、開花からなんと約50日ほどで収穫が可能に!5~6月に苗を植え付けて7月には収穫できます。
基本はつるを1~3本仕立てにして、つるの伸びに合わせてひもなどで支柱に固定をして誘引をします。枝や葉が密になり過ぎずないよう、風通しよく育てることがポイント◎
主枝に栄養を回して早く実を付けさせたいので、わき芽は手で自然に折り取れる時期に早めに取っておきましょう。その際にハサミを使うと、刃から病気が伝染するリスクが高まるので、ハサミはできるだけ使わないようにしてくださいね!
種から育てるより、お店に売ってある苗から育てたほうが簡単に育てることができるので、気軽に始めてみることができます。
ニラ

ニラは野菜のなかでは数少ない多年草という種類なので、冬を越えて数年間は同じ株で育てることができます。ニラは酸性度を嫌い、pH6以下だと育ちが悪くなるので、酸性の土はできるだけ避けてくださいね。
春から夏の生育がいい時期に葉だけを収穫し、冬は休眠させるようにします。比較的寒さには強く、夏季、気温が高くなると生育は早くなるのですが、葉が細く、薄くなります。
花芽は日の長い日・気温の高い7~8月にトウ立ち・開花し、1年目は収穫せずに株を大きくして、2年目の春〜夏にかけて収穫します。葉を収穫するときは地上部を2〜3cm残してはさみで刈り取ると、20日ほどで再生するので長く楽しめますね◎一株で何度も収穫することができるのもポイント。
ニラの花は白くてかわいらしいので、花が咲いている時期も目でも楽しむことができます♩
ナス

夏の暑さにもよく耐え、雨にも比較的強いので、とても育てやすい野菜です!栄養がたくさんある、水分の多い土が適しています。
日当たりのよい場所で育てましょう。日照時間が長く、日射量が多いほど収穫量が多くなります◎
「ナスは水で育つ」と言われている野菜なので、水が不足すると育ちが悪くなり、収穫量が上がらなくなってしまいます。それだけでなく、ナスにツヤがなくなってしまったり、ハダニ類の被害も多くなるので、注意が必要です。
開花後15~20日前後で収穫できます。収穫のタイミングは、夏の朝の涼しい時間帯に収穫すると日もちがよくなりますので、ぜひお試しください!
オクラ

オクラは暑さには強いのですが、寒さには弱いので、10℃以下では生育できなくなります。。。なので夏にぴったりの野菜ですね◎
日当たりのいい、栄養がたっぷりある、水はけのよい畑で育てましょう。ニラと同様に酸性の土はできるだけ避けてください。
乾燥し過ぎてしまうとオクラが大きく育たないので、適度な水やりを忘れないようにしましょう。
収穫時期は品種によって違いがあるのですが、開花後4~5日くらいで5~8cmくらいの若サヤを収穫するのがいいです!収穫が遅れると、実がとても硬くなってしまうので注意が必要です。
オクラを収穫した後は風通しを良くするために、収穫した果実の下の葉を全て摘み取っておくようにしましょう。切り取らずにそのままにしてしまうと、養分や水分などが葉の方に流れてしまい、その後の実成りが悪くなってしまうので気を付けてくださいね!
オクラは蕾を天ぷらにしたり、オクラを食べるときは茹でることが多いですが、オリーブオイルで焼いて仕上げに塩を少々振って出来る、焼きオクラもおすすめです♩
バジル

庭で育てておくと便利なバジルはイタリア料理には欠かせないハーブの一つです。爽やかな香りが食欲をそそり、ジェノベーゼソースやパスタ、ピザの彩りに最適です◎
バジルはお日様が大好きです。日当り、風通しの良いところで育てましょう。
気温が高くなってくると、次々と新しい葉っぱを出して成長します。そのまま茎を切らずに伸ばしていくと、7月後半から8月にかけて花が咲きますが、花を咲かせると葉が固くなってしまい味も落ちてくるので、適切なタイミングに摘芯という剪定作業をしていくことが必要になります。
剪定作業は、草丈が20cmくらいまで生長したら摘心をして側芽の生長を促します。地面から2~3節目の少し上のあたりを清潔なハサミで切ります。収穫もかねて切り戻すようにするとよいでしょう。
摘芯をすると、1本だった茎が2本になり、この摘芯作業を繰り返すと、茎が倍々に増えていくので、収穫量も増えます!摘芯をしないで花を咲かせてしまうと、8月ごろに種をつけた後、急に元気がなくなってきますが、摘芯をすることで次の花を咲かせるために新しい葉を出していくので、収穫時期が伸び、収穫量も増えます!摘芯することで、長くたくさん収穫できるのです◎
まとめ
初めての野菜作り。うまくいけば自信がついて、「次はこれを育てようかな?」と、新たな目標が生まれ、野菜作りがどんどん楽しくなってきます!
もし失敗してしまっても、葉物野菜やミニ野菜は育てられる期間が長いので、すぐにリトライすることが可能です。
植え付け方や置き場所、水やりの仕方、剪定方法など、失敗の原因を探っていくと、次はきっと成功するはずです☆
種をまいてじっくり育ててみるのもよし、買ってきた苗を植え替えすれば、より確実で簡単に野菜を育てることができます。
ぜひ種や苗を植えて、自分で作った野菜を味わってみてはいかがでしょうか♩
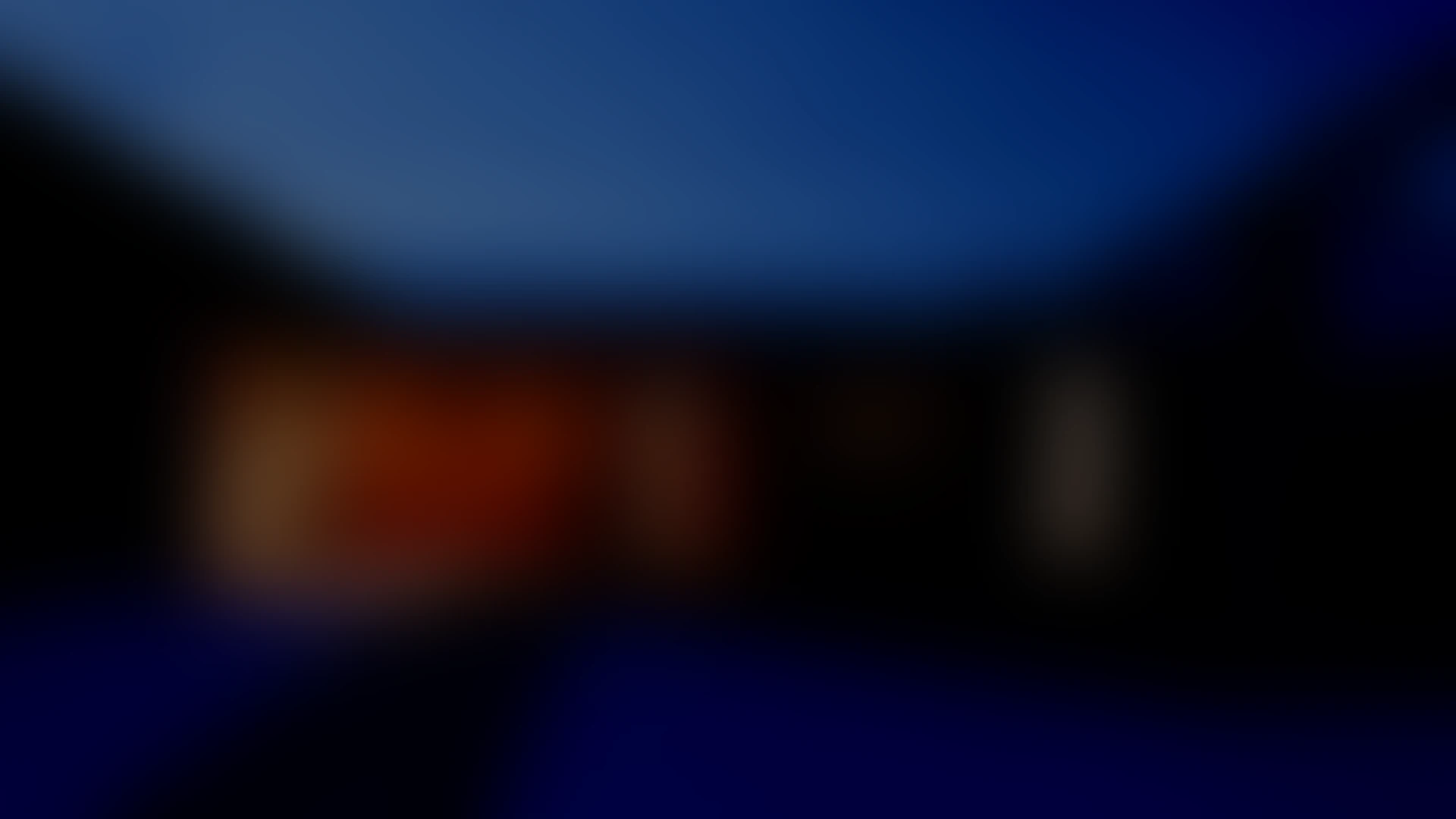



















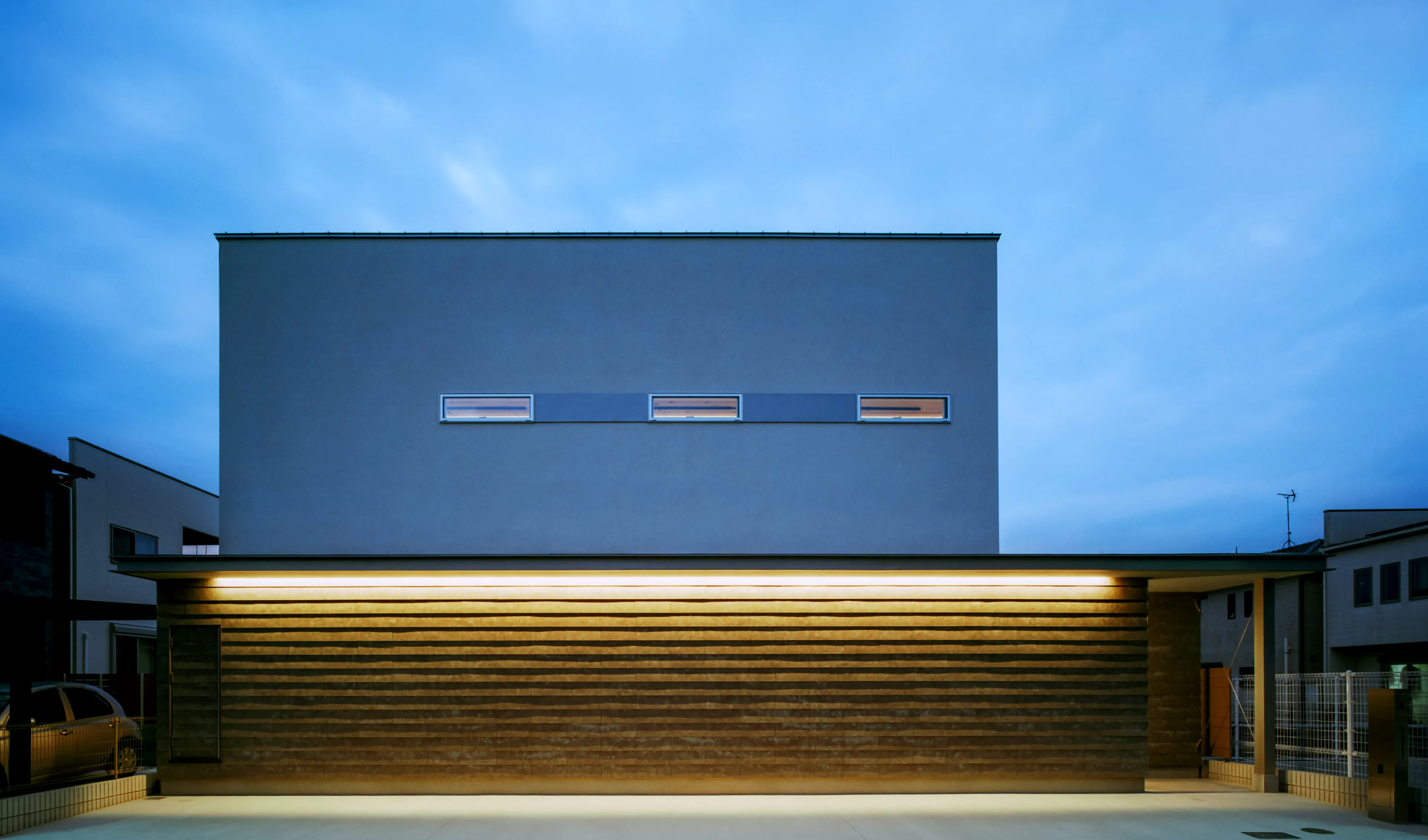

























 『今オススメの樹木・野菜』で紹介した、イロハモミジやキンモクセイ。モミジは秋の季節に色づいて、緑色だった葉が黄色、赤色に変化していく様子は眺めていると自然を身近に感じることができます。モデルハウス「kokage Salon」にあるモミジも赤色に変化して毎日の癒しになっています♪
『今オススメの樹木・野菜』で紹介した、イロハモミジやキンモクセイ。モミジは秋の季節に色づいて、緑色だった葉が黄色、赤色に変化していく様子は眺めていると自然を身近に感じることができます。モデルハウス「kokage Salon」にあるモミジも赤色に変化して毎日の癒しになっています♪